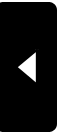センター試験がなくなります!
学習塾マイポートの塾長 平野です。
あっという間にお正月三箇日もおしまいですね。
今年のお正月は初詣に外に出た以外はずっと引きこもり生活でした。
体重がえらいことになっていそうです。。。
さて、前回は今年マイポートが変わると書きました。
実はそれには深い理由があるのです。
今回の記事は長くなりますが、特に小学生以下のお子さんをもつ親さんには是非読んで知っておいて頂きたい内容です。
当ブログをご覧のみなさんは子育て、教育に興味がある方ばかりだと思います。
ですので、2020年を最後にセンター試験が最後となるのはご存知の方も少なくないでしょうね。
でも、全く初耳の方はたぶんビックリですよね。
2020年以降の大学入試改革は私たちが想像もつかないような大改革となるようです。
この改革は『明治維新以降または戦後最大の教育改革』と表現する人もいるくらいの規模のものです。
すごくざっくりと、わかりやすく説明するなら
『大学入試で問われる内容が180度変わり、今までの学習形態、方法、システムがほとんど役に立たなくなる』ということです。
今までの受験は知識・技能の高さを問われました。
しかし、文科省は今度の入試改革において知識・技能だけでなく 思考力・判断力・表現力 という3つの力を求めるようはっきりと打ち出してきたのです。
英語に例えていうと
「読む」「書く」中心の入試から、「聞く」「話す」を加えた4つの力が求められるようになるのです。
実際に英語を仕事レベルで使うとなると、読んで 書けて だけでは事足りませんね。
聞いて 話す というコミュニケーションが出来なければ役に立ちません。
当然、仕事におけるコミュニケーションには思考力、判断力、プレゼン力が必要になってきます。
つまり、将来本当に使えるレベルの総合的な英語力が入試において問われてくるのです。
他教科に関しても、暗記して公式覚えてドリル練習繰り返して のような従来の勉強では全くが立たない入試形式にガラッと変わってしまうのです。
さあ、大学入試がこのように変わるとなると当然、高校はもちろん中学以下も授業システムは変わってくるはずです。
実際、私立学校や公立の中高一貫校はこの改革の流れに対応するべく動き出しています。
しかし、普通の公立学校はこの動きに対応したくとも大胆に対応しにくいのが現状のようです。
なぜなら、私立校や中高一貫校は高校受験がないため2020年以降に照準をしぼって授業カリキュラムを作る事ができます。
ところが公立中学の場合は現行の知識・技能を問う高校入試が2020年まで続いていくために大胆な対策がとれないのです。
果たして高山はどうでしょう?
私たちのこどもたちは住んでいる場所、教育環境が違っても同じ大学を同じ試験で受けなければなりません。
大変失礼な言い方で申し訳ないですが
地元の小中学校が将来の入試大改革にまともに順応できる体制になるにはかなりの時間が必要だと思っています。
事実、高山の中学校の英語の定期テストなんかは教科書を暗記していけば点数がとれますが
私が塾を経営していた横浜では教科書からはほとんどでないようです。
都会だと公立中学でも入試改革を意識した授業やテストになってきているのです。
さてさて、今回のお話でお母さんお父さんの中には不安が高まっている方がいらっしゃることでしょう。
私も小学生の子をもつ親ですのでかなり不安を持っています。
親が不安を持っても持たなくても
お子さんが中学2年生以下の場合、否応無しに新しい試験に立ち向かっていかなければならないのです。
知識と技能は暗記とドリルの繰り返しでなんとかなるでしょう。
ではお子さんに 思考力 判断力 表現力 は培われていますか?
知識と技能を自ら高めていく主体性は育まれていますか?
やればできる や やるきスイッチでなんとかなるようなハードルではないのです。
小学生の低学年までに土台となる 力 をつけていかないと到底間に合わないような時代がやがて必ずきます。
なぜマイポートは変わるのか?
それは大学入試の大改革に立ち向かわなければならないからです。
中3、高3になってあわてて塾に駆け込んでもなんともならない時代がやってくるからです。
今 始めなければ間に合わない 本当の力がつかないからです。
私の息子は今 小1です。
将来、私の息子がどんな選択もできるよう、新しい入試改革で求められる力をマイポートで養ってあげたい。
それだけでなく、高山に住む子どもが都会の子どもと比べてハンデとならないような学びの場を作りたい。
そのためにマイポートは今春生まれ変わるのです。
では、次回もう少し突っ込んでセンター試験に変わる入試制度についてご紹介していきます。

あっという間にお正月三箇日もおしまいですね。
今年のお正月は初詣に外に出た以外はずっと引きこもり生活でした。
体重がえらいことになっていそうです。。。
さて、前回は今年マイポートが変わると書きました。
実はそれには深い理由があるのです。
今回の記事は長くなりますが、特に小学生以下のお子さんをもつ親さんには是非読んで知っておいて頂きたい内容です。
当ブログをご覧のみなさんは子育て、教育に興味がある方ばかりだと思います。
ですので、2020年を最後にセンター試験が最後となるのはご存知の方も少なくないでしょうね。
でも、全く初耳の方はたぶんビックリですよね。
2020年以降の大学入試改革は私たちが想像もつかないような大改革となるようです。
この改革は『明治維新以降または戦後最大の教育改革』と表現する人もいるくらいの規模のものです。
すごくざっくりと、わかりやすく説明するなら
『大学入試で問われる内容が180度変わり、今までの学習形態、方法、システムがほとんど役に立たなくなる』ということです。
今までの受験は知識・技能の高さを問われました。
しかし、文科省は今度の入試改革において知識・技能だけでなく 思考力・判断力・表現力 という3つの力を求めるようはっきりと打ち出してきたのです。
英語に例えていうと
「読む」「書く」中心の入試から、「聞く」「話す」を加えた4つの力が求められるようになるのです。
実際に英語を仕事レベルで使うとなると、読んで 書けて だけでは事足りませんね。
聞いて 話す というコミュニケーションが出来なければ役に立ちません。
当然、仕事におけるコミュニケーションには思考力、判断力、プレゼン力が必要になってきます。
つまり、将来本当に使えるレベルの総合的な英語力が入試において問われてくるのです。
他教科に関しても、暗記して公式覚えてドリル練習繰り返して のような従来の勉強では全くが立たない入試形式にガラッと変わってしまうのです。
さあ、大学入試がこのように変わるとなると当然、高校はもちろん中学以下も授業システムは変わってくるはずです。
実際、私立学校や公立の中高一貫校はこの改革の流れに対応するべく動き出しています。
しかし、普通の公立学校はこの動きに対応したくとも大胆に対応しにくいのが現状のようです。
なぜなら、私立校や中高一貫校は高校受験がないため2020年以降に照準をしぼって授業カリキュラムを作る事ができます。
ところが公立中学の場合は現行の知識・技能を問う高校入試が2020年まで続いていくために大胆な対策がとれないのです。
果たして高山はどうでしょう?
私たちのこどもたちは住んでいる場所、教育環境が違っても同じ大学を同じ試験で受けなければなりません。
大変失礼な言い方で申し訳ないですが
地元の小中学校が将来の入試大改革にまともに順応できる体制になるにはかなりの時間が必要だと思っています。
事実、高山の中学校の英語の定期テストなんかは教科書を暗記していけば点数がとれますが
私が塾を経営していた横浜では教科書からはほとんどでないようです。
都会だと公立中学でも入試改革を意識した授業やテストになってきているのです。
さてさて、今回のお話でお母さんお父さんの中には不安が高まっている方がいらっしゃることでしょう。
私も小学生の子をもつ親ですのでかなり不安を持っています。
親が不安を持っても持たなくても
お子さんが中学2年生以下の場合、否応無しに新しい試験に立ち向かっていかなければならないのです。
知識と技能は暗記とドリルの繰り返しでなんとかなるでしょう。
ではお子さんに 思考力 判断力 表現力 は培われていますか?
知識と技能を自ら高めていく主体性は育まれていますか?
やればできる や やるきスイッチでなんとかなるようなハードルではないのです。
小学生の低学年までに土台となる 力 をつけていかないと到底間に合わないような時代がやがて必ずきます。
なぜマイポートは変わるのか?
それは大学入試の大改革に立ち向かわなければならないからです。
中3、高3になってあわてて塾に駆け込んでもなんともならない時代がやってくるからです。
今 始めなければ間に合わない 本当の力がつかないからです。
私の息子は今 小1です。
将来、私の息子がどんな選択もできるよう、新しい入試改革で求められる力をマイポートで養ってあげたい。
それだけでなく、高山に住む子どもが都会の子どもと比べてハンデとならないような学びの場を作りたい。
そのためにマイポートは今春生まれ変わるのです。
では、次回もう少し突っ込んでセンター試験に変わる入試制度についてご紹介していきます。